医療秘書の専門学校では、何が学べるの?
京都栄養医療専門学校には、医療事務・医療秘書科という、2年制の学科があります。
医療事務を目指せる教育機関や習得方法はさまざまですが、医療事務に必須とされる事務処理能力、診療報酬請求事務能力、IT処理技術などの他、秘書としてのマナーやスキルを身に付けることができる学科です。
目次
医療秘書の専門学校 どんなコースがあるの?
京都栄養医療専門学校の医療事務・医療秘書科は、2年制。
1年次には医療事務として必要な基礎的な知識と技能を学び、2年次からは、3つのコースに分かれ、それぞれのコースで専門的な知識や技能を習得していきます。
コースは大きく2つ
まず1つ目は、医療事務コースです。
このコースでは、医療機関などで活躍できる医療事務のスペシャリストを目指します。
求められるスキルは、正確でスムーズに医療費を計算し、保険機関に請求をすること。
患者さんごとにかかった医療費(健康保険を利用する医療費は、正確には診療報酬といいます)の計算、医療機関の中で発生するさまざまな電子文書の作成など、医療機関などで必要となる、事務処理を行うためのスキルを習得します。

2つ目の病院受付・クラークコースでは、患者さんを思いやり、医療スタッフに信頼される人材を育成します。 その名の通り、医療機関の受付窓口、病棟や外来でのクラーク業務などに必要なスキルを身につけます。
これには、医療事務としての基本的なスキルもさることながら、医療機関で働くために必要とされるメディカルマナー、医療機関内外で必要となる事務処理能力、介護などの専門的な知識や実務能力なども、学んでいくことになります。

秘書とはクラークのこと
ではこのうち、医療秘書にあたるのはどのコースでしょうか。
正解は2つ目の「受付・クラークコース」です。
もちろん、他の2つのコースで学んでも、将来的に医療秘書として就職することは出来ますが、受付・クラークコースでは、より専門性の高いスキルを身に付けることができます。カリキュラムの一例を見てみましょう。
- ●調剤報酬請求事務
- ●レセプト点検基礎
- ●病院受付事務
- ◇医療事務職のための医学知識(外科系)
- ◇からだの仕組みと働き
- ◇医療事務職のための検査学
- ◇介護の基礎
- ★秘書検定対策講座
- ★メディカルホスピタリティ
- ★秘書実務演習
- ★病棟クラーク演習 など
これらのうち、「●」となっているカリキュラムは、医療事務として働くために必要な基礎的なことを学びます。 「◇」となっているカリキュラムは、医療機関で働くための必要な医学的な知識を学びます。 そして「★」となっているカリキュラム、これが医療秘書やメディカルクラーク、病棟クラークと呼ばれる職業に必要とされる、専門的な知識と技能を学ぶ時間です。
クラークとはそもそも、「書記」「事務員」「店員」などを指す英語です。例えば、医療に限ったことではありませんが、何かしらの特別な業務に専念する人を支える仕事として、秘書があります。「社長秘書」は、社長が本来の業務に専念できるよう、事務的な作業を一気に引き受ける職業です。
では、医療機関ではどうでしょうか。 医療機関の中には、医師や看護師などの医療スタッフがたくさんいます。
医療スタッフの本来の仕事は、患者さんに医療サービスを提供することなのですが、そのためには、さまざまな「記録」を残していく必要があります。
また、診察の受付、検査や治療に関する指示書、そしてその検査の結果など、さまざまな情報を記録していく必要があります。
これらは事務的な作業であり、医療スタッフが本来の業務に集中できる環境を整えるために事務作業を一手に引き受けるのが、病棟や外来にいる「クラーク」なのです。クラークという言葉の本来の意味、「書記」や「事務員」と呼ばれる職業であることが、分かりますよね。
医療秘書の専門学校、何を学べるの?
医療秘書(=メディカルクラーク)は、患者さんや医療スタッフに信頼される、病院受付・クラーク業務のスペシャリストです。
京都栄養医療専門学校では、病院受付・クラークコースに対し、大きく3つの分野における知識と技能を習得できるよう、カリキュラムを設定しています。
医療の概略

医療機関で働くことを目指す以上、医療機関のもつ独特の世界観や環境を知っておく必要があります。 例えば、「医療」とはそもそも何を示すのか、「医療」や「医学」はどのように発展してきたのか、現在の医療機関はどのように運営されているのかなど、「医療」にまつわるさまざまなことを学びます。
また、「医療スタッフ」と一言でいっても、その職種や仕事の内容は実にさまざま。
医療に関する資格は国家資格であることがほとんどですので、それぞれの役割が明確に決まっています。実際に医療機関で働くことになれば、このような医療スタッフとも、日々のコミュニケーションは欠かせません。
円滑に仕事を進めていくためにも、「医療」という分野、そこで働くスペシャリストたちのことも、学んでおく必要があります。
医療情報を扱うために必要な最低限の医学知識
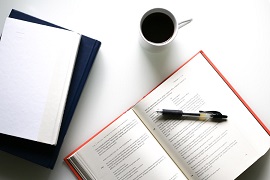
医療秘書が業務上で扱う情報は、患者さんの個人情報から、医療用語や検査・処置の内容にいたるまで、実にたくさんの情報があります。
医療スタッフとなるために学んできた人たちにはあたり前のことでも、事務作業のプロとして学ぶ医療事務や医療秘書にとっては、まったく未知の情報であることもあります。
医師や看護師が何を言っているのか分からない、患者さんが何かを訴えかけてもその理由や大変さがわかない、こういう状況では、医療機関内での仕事を正確にスムーズに進めることは、できませんよね。
医療事務や医療秘書は、事務作業のプロとはいえ、「医療」の分野で働くわけですから、やはり「人のからだの仕組みや働き」についても、ある程度は知っておく必要があります。
京都栄養医療専門学校では、医療秘書を目指すため、次のようなカリキュラムを組んでいます。
- 医療事務職のための医学知識(外科系)
- からだの仕組みと働き
- 医療事務職のための検査学
- 介護の基礎
ここまでは、前述の通りです。このほかには
- 医療事務職のための医学用語
- 医療事務職のための医学知識(内科学)
- 医療事務職のための薬理学
なども学んでいくことになります。
からだの仕組みや働きを知るためには、「なぜそうなるのか」という理由を知ることが必要です。例えば「頭が痛い」という症状には、「なぜ頭が痛くなるのか、頭が痛いと感じるのか」という理由があります。これらを知ることで、その時の患者さんの状態に合わせた対応が、可能になるのです。
また、医師や看護師などの医療スタッフの間で交わされる、医療用語。これらがまったく分からなければ、会話すら成り立ちませんよね。
医療秘書として、正確にスムーズな対応をするには、医療スタッフが交わしている言葉の意味を理解し、自分の仕事へも生かして行く必要があります。
秘書としての役割、立ち居振る舞い

そしてもう一つ、医療秘書として必要とされるのが、秘書としての役割や立ち居振る舞いです。 皆さんは、「秘書として立ち居振る舞い」と聞くと、どのような姿を思い浮かべるでしょうか。例えば
- 立ち姿、座った姿ともに、背筋が伸びて姿勢が良い事
- 丁寧な言葉遣い
- 相手の名前などを間違えない
- いつも自然な笑顔で話をする
- 必要なシーンでは引き締まった顔で、相手に誠心誠意お詫びをする
など、品の良さがにじみ出るような立ち居振る舞いを思い浮かべる人は、多いのではないでしょうか。
医療秘書も同様に、こうした立ち居振る舞いが出来る人材が求められます。医療秘書は、その医療機関の中で、最初に患者さんと接する可能性があるポジションです。外来クラーク、病棟クラーク、後述するドクタークラークは最初ではないかもしれませんが、いずれにしても患者さんに対して失礼が無いこと、他の医療スタッフとも円滑なコミュニケーションを取ること、場合によっては他の医療機関の人とも円滑なコミュニケーションを取ることが求められます。そうした中で、誰に対しても気持ちの良い対応ができることは、とても大事なスキルなのです。
医療秘書専門学校を出ると、何ができるの?
その名の通り「医療秘書」として働くことができます。カリキュラムの中では、病院受付や医療事務に関することを学ぶ講義もありますが、特徴的な職種としては、メディカルクラークとドクターズクラークがあります。
メディカルクラーク
メディカルクラークとは、病棟や外来に勤務するクラークです。医療秘書の中でも、医療の中心的なポジションといえるかもしれません。メディカルクラークの仕事は、診療報酬請求事務や、医療機関としての「良質なサービス」である患者さんへの接遇、診療内容に関する文書作成・管理などがあります。診療報酬請求事務は、医療機関の収入に直結するため、ミスや勘違いは許されません。正確かつスピーディーな仕事が求められます。 患者さんへの接遇としては、医療機関内外からの電話応対、患者さんと対面での受付業務や誘導、必要書類などの受け渡しなどがあります。患者さんからみれば、最初に電話に出た人の対応や、病棟・外来の窓口での対応など、さまざまなシーンでの「接遇」がその医療機関に好感を持つかどうかのヒントになります。 診療内容に関する文書作成・管理は、医師が記載した診断書を管理して患者さんに渡したり、患者さんから希望のあった書類への記載を依頼し、それを患者さんに手渡すまでの一連の流れです。医療機関で作成される書類は、秘匿性が非常に高く、確実にそれを必要とする患者さんの手元に、届ける必要があります。 メディカルクラークには、こうした仕事に対し、より質の高い専門技能が求められています。
ドクターズクラーク
ドクターズクラークは、メディカルクラークともよく似ているのですが、扱う情報の出所が「医師」である点が大きく違います。ドクターズクラークは、日本語に直すと「医師事務作業補助者」といい、文字通り、医師が行うべき事務作業を補助するという仕事です。
医師は、日常的な診療を行う中で、実に多くの事務処理を必要とします。
外来や病棟で自分が行った診療内容についての記録(紙カルテの場合と電子カルテの場合がある)、具体的には、患者さんの訴え、患者さんに必要な検査、処方の内容、行った処置、使用した薬剤等のオーダーなどがあります。その他にも、診断書や紹介状、診療内容の概要をまとめたサマリー作成などを行っています。
これらの事務作業に対する負担を減らし、特に病院に勤務する医師の仕事を支援する意味で、「医療事務作業補助者」という仕事が生まれました。 近年特に、この仕事に対する注目は高まっており、具体的な業務として患者さんに必要な検査、処方箋、次回予約、行った処置、使用した薬剤等のオーダーや、診察記録の代行入力を行います。
ドクターズクラークは、これらの仕事を行いながら、看護師やその他の医療スタッフと連携をとること、患者さんを診察室へ案内することなども業務に含まれてきます。
医師の診療や診察に対する知識はもちろんの事、パソコン操作のスキル、高いコミュニケーション能力も、必要不可欠とされます
いかがでしょうか。医療秘書の専門学校では、実にたくさんのことを学ぶことができます。
将来、自分がどのような現場で働きたいのか、そのような仕事を選択したいのか、じっくりと考えながら、多くの知識やスキルを自分のものにしていきましょう。
進路に関する相談や質問など、公式LINEでお気軽にお問い合わせください。
【学校法人大和学園 京都栄養医療専門学校】
以下の学科をもつ、京都・嵐山にある専門学校。
●管理栄養士科[4年制]
●栄養士科[2年制]
●管理栄養士科3年次編入学
●医療事務・医療秘書科[2年制]
●診療情報管理士科[3年制]
