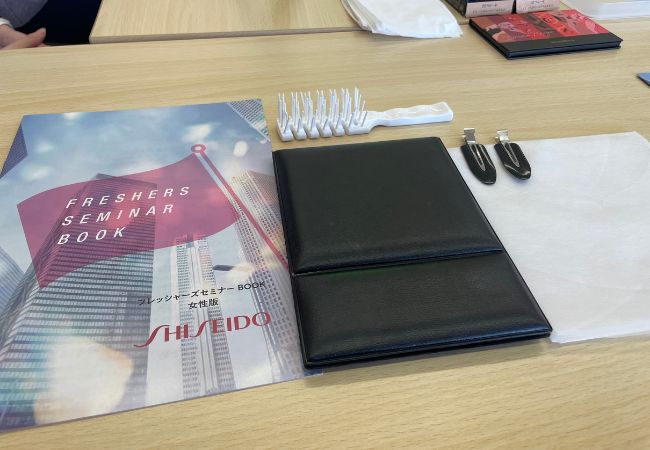【栄養士科】こどものための食育実習~アレルギー対応献立と基本献立~
みなさんこんにちは
京都栄養医療専門学校です 

暑い日が続きますが、みなさん夏バテにはご用心ください!

さて、今回ご紹介する授業は「こどもの食物アレルギーに対応した食事づくり」です
「こどもたちに安心・安全・美味しい食事を提供できる栄養士に興味がある!」という方は必見
栄養士科2年生保育園栄養士コースの実習を少しだけ覗いてみましょう
本日のテーマは
「基本献立(卵・乳・小麦アレルギーでない子の食事)と、
卵・乳・小麦アレルギーの対応献立を同時に、かつ安全に作る調理する!」
メニューはみんな大好きハンバーグ

アレルギーがあるこどもたちが安心して食べられるよう、どのような食材で調理されているのかな?
☆献立のポイント~材料の置き換え(代替)~
・基本献立にも、もともと卵を含まない献立にする
・ハンバーグで使用する【パン粉(小麦)】を【じゃがいものペースト】へ変更
・シチューで使う【牛乳(乳)】を【豆乳】へ変更
・シチューは、基本献立でも小麦のルウを使わず米粉を使って、作り分けの種類を減らす
(調理が複雑にならず、小麦アレルギーのみのお子さんが牛乳でカルシウムをとれる)

☆調理するときのポイント①~見分けやすくする(誤配・誤食防止)~
基本献立と対応献立の誤配(まちがって配膳してしまう)、誤食(まちがって食べてしまう)を
防止するため、基本献立と対応献立で「ハンバーグの成型(個数)」と「食器の絵柄」「トレーの色」を分ける
例えば、
◎ 基本献立〈スヌーピーの器&ハンバーグ1個、ピンク色トレー〉
◎ 対応献立〈スヌーピー以外の器&ハンバーグ2個分け、黄色トレー〉

☆調理するときのポイント②~調理を分ける(コンタミネーション防止)~
基本献立と対応献立のコンタミネーション(混入・混ざってしまうこと)を
防止するため、基本献立の担当者や原因食物を使うタイミングを分けて調理する。
(今回対応献立を担当した学生は、帽子に赤いシールを付けて区別しています )
)

☆調理するときのポイント③④~基本献立・対応献立共通~
・こどもたちが食べやすいように小さくカット
・リンゴの皮は残食や衛生面の観点からすべて剥くこと

いかがでしたか?
同じハンバーグでも食材の種類や調理過程で
様々な工夫がされていることが分かりましたね

こどもたちが笑顔で成長できるよう栄養士は見えないところで日々活躍しているのです



もっと詳しく栄養士のことが知りたい方は、
Click!