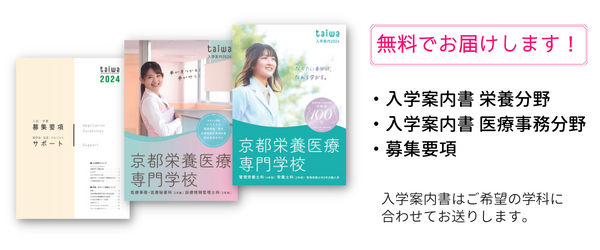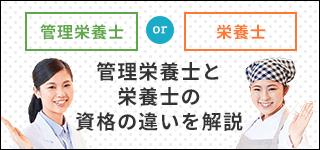管理栄養士の需要ってどれくらいあるんだろう?
健康の源って何?と考えたとき、それは「食」だという方もいます。
「食」から健康を支える仕事、それこそが管理栄養士の仕事です。
管理栄養士の需要について調べてみました
「管理栄養士」は厚生労働大臣が認定する国家資格です。
仕事の内容としては、大きくはこの2種類のことを行います。
この2種類からいろいろな仕事内容に細かく派生していきます。
- 食事や栄養の指導
- 食事や栄養の管理
よく似た職業で、「栄養士」もありますよね。
こちらも「管理栄養士」と同様、食から健康を支えるお仕事です。
では、「栄養士」と「管理栄養士」の仕事には、どのような違いがあるのでしょうか。
まず大きな違いは、「誰から認められるか」という点です。いずれの資格とも国家資格ではありますが、栄養士は都道府県知事からの免許、管理栄養士は厚生労働大臣からの免許、という違いがあります。
栄養士の業務内容としては、
●栄養学に基づいた、栄養面からの健康的な食生活のアドバイザー
●栄養バランスのとれた献立(メニュー)の作成、調理方法の改善などをおこなう
●傷病者の療養のための栄養指導
●配慮が必要な人を対象にした給食管理や指導
●栄養指導のための企画
●大規模給食施設での管理業務や労務管理
などがあり、管理栄養士の業務と被るものもあります。
しかし、一定の規模の給食施設や傷病者や高齢者などが対象の給食施設では、「管理栄養士」を置くことが義務付けられたり、いくつかの条件下ではありますが、医療機関において「管理栄養士」が栄養指導などを行うと、保険点数を算定できる(医療機関にとっての収入となる)ようになるなど、「管理栄養士」にしかできない仕事も、世の中にはあります。
管理栄養士の需要はこんなにある!

では管理栄養士の資格を取ったあと、実際にはどんなところで仕事をしているのでしょうか。
働き方はさまざまですが、次のようなところに、管理栄養士の需要があるようです。
- 医療機関、医療現場
栄養や食のスペシャリストとして医療の現場で活躍できることが管理栄養士の特徴ということで、やはり医療機関での仕事の需要は多いようです。
入院患者さんの栄養管理や通院患者さんの食事指導などはもちろんですが、最近では、チーム医療を実践している病院が増えていて、特に「NST=Nutrition Support Team(栄養サポートチーム)」では医師・看護師・薬剤師などの他の専門職と連携して、患者さんに適切な栄養管理を行います。
チームが稼働すると、保険点数が算定されて医療機関の収入につながります。
また、管理栄養士が食事計画に基づき栄養食事指導を行うことで、さらに点数が加算される仕組みになっています。
- 介護施設・福祉施設
超高齢化社会を突き進んでいる日本では、すでに多くの介護施設があります。
その種類もいくつかにわかれていますが、介護施設での栄養指導や食事の管理は、利用者である高齢者にとってとても重要です。
また障がい者(児)の施設も同様に、その人の身体機能に合った食事のサポートは必須です。
どちらの施設も、単に栄養価だけでなく、その人の食べる意欲や喜びを引き出すような、そんなサポートができたらいいですよね。
- 社員食堂や社員寮、学校、学生食堂や学生寮
多くの社員を抱える企業や、学生を抱える学校にとって、本来の目的をしっかり達成するために健康を維持させることは、大きな課題だと思います。
企業では幅広い世代の人たちが働いていて、その一人ひとりの状況を考えて、より健康に仕事をしてもらえるように献立を考えたり、食事を提供したり、アドバイスをしたりと、その需要は大きいと思います。
学校では何より栄養を必要としている世代の、食欲を満たしながらも、美味しく、栄養バランスの整った食事の提供や、学年や年齢に合ったメニューの構成など、成長が見られる世代を食でサポートできる、そんな職場ではないでしょうか。
- 地域、行政、研究機関
保健センターや保健所などは地域の乳幼児から高齢者までを対象にしているので、地域に住まわれる人たちにとって、健康について考えるいちばん身近な場所かもしれません。
このような施設で、さまざまな世代の栄養や食事についての相談に対応したり、講習会を開いたりすることで、栄養について広く正しく知ってもらうことが、健康な生活を送ってもらうことにつながると思います。
同様に、地域住民に対しての指導という意味では、都道府県や市町村からの需要もあります。
他にも、アスリートをサポートする仕事や薬局などにも活躍の場が広がっているようです
管理栄養士は需要のある仕事、頑張って勉強しよう!
やはり、専門性が高い管理栄養士になるためには、しっかりした勉強が必要になります。
栄養士でも管理栄養士でも、通信教育は認められていませんので、まずは実際に養成学校に通って、決められた単位を取ること。
この単位をきちんと取れれば栄養士の資格は取れます。
管理栄養士に関しては、栄養士の資格を取っていることが条件で、その上で、実務経験を積むか、管理栄養士養成学校で勉強を続けて、国家試験に合格して、やっとその資格を手に入れることができます。
SNSで最新情報をみる
京都栄養生の日常や授業の様子、入学をお考えの方の気になる情報などをお届け★
フォローして最新情報をゲットしよう!

進路に関する相談や質問など、公式LINEでお気軽にお問い合わせください。
【学校法人大和学園 京都栄養医療専門学校】
以下の学科をもつ、京都・嵐山にある専門学校。
●管理栄養士科[4年制]
●栄養士科[2年制]
●管理栄養士科3年次編入学
●医療事務・医療秘書科[2年制]
●診療情報管理士科[3年制]
京都栄養で栄養士・管理栄養士をめざす!
京都栄養医療専門学校のカリキュラムで夢を実現しませんか?
目的に合わせて2つの学科からお選びください。
お電話・お問い合わせはこちら